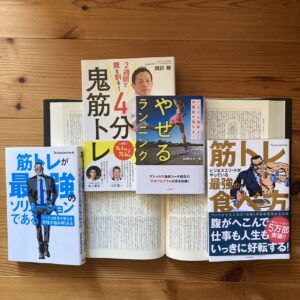SR500の思い出(1)排気量とキックスタート
SR400の打ち間違えではない。今どきの人はご存じないと思うが、1999年まではSRには400と500があったのだ。
ヤマハのSR400は言わずと知れた超ロングセラーモデルのバイクであるが、このたびいよいよ国内向けの生産終了が発表された。寂しい限りではあるが、むしろ43年もの長きにわたり愛されてきたSRを作り続けてくれたヤマハには感謝しかない。ありがとうヤマハ。
そして同時にFinal Editionの発売も告知され、まだまだ新車でSRに乗れるチャンスも残されている。
そこで今回は過去にヤマハSRに乗っていたひとりとしてその魅力を熱く語ろうと思ったが、私は400に乗ったことがないので比較しての説明が出来ない。そしてそれ以前に特にバイクの技術に詳しい訳でもないので性能的な説明も出来ない。
しかも乗っていたのは2年間だけで中古で購入。
それでもSRについて私が体験したことと考えたことを書いてみることにした。
SRを褒めまくる内容ではないので、SR400をこれから購入する人の後押しになるかも分からないが、少しでもSRに興味がある人に何らかのヒントになればうれしいと思う。
バイクはあんまり詳しくないけど、バイクに・SRに興味あるぞというあなたに向けて。
しばしお付き合いを。
さて、最初に数字の話から。
先ほどから500だの400だのと言っているのは、エンジンの排気量であり、500は500㏄、400は400㏄のことを指す。ちなみに一番小さなバイクは50㏄で軽自動車が660㏄。
つまりSR500と400の一番の違いはこのエンジンの排気量の違い。そしてその他はほとんど変わらないので見た目での区別はまずつかない。しかもその違いはたったの100㏄。
バイクに興味がない人にとって数字の100違いに深い意味を感じられないと思うが、バイク乗りにとってはこの100の差は大きなものがある。
そう免許区分が違うのだ。いわゆる大型と中型。400が普通二輪免許で運転が出来るのに対して500は大型二輪免許が必要。
つまり普通二輪免許(いわゆる中免)のみの人は500を選ばない・選べない。大型免許を持っている人が選ぶバイク。
では大型免許を持っている人がSR500を選ぶのかというと(そうではあるのだが)、これまた微妙である。なぜかと言えば、500㏄はやはり微妙な排気量なのだ。つまりせっかく大型二輪免許を手にしたならばもっと大きい排気量に乗りたくなるのが人情。
例えばナナハン。古い呼び方になるが750㏄のことをこう呼び、大型の教習者もこの排気量が多いと思う。大型らしさと扱いやすさのバランスが良い排気量である。
そして大型の中でも大き目の排気量の目安が、リッターオーバー。つまり1000㏄以上の排気量。このクラスであればいかにも大型バイクらしい見た目とともに所有する喜びもまた格別なものがあると思う。
ここまでの説明で何となく察しがついていることと思うが、そう実はSR500はあまり人気がないバイク。もう少し詳しくいうと、このバイクを嫌いな人は少ないが購入する人も少ないという絶妙な不人気だと感じている。
さらに販売終了から20年以上も経った今では中古車の数も減ってきており、500を選ぶ人はかなり少数派であろう。そんな少数派になるかならないかで悩んでいる人に向けて500の魅力を語るべきなのだが、前述の通りで400に乗ったことのない私には違いを語れない。
しかしながら、性能面では100㏄の差はそれほど大きなものではないと推測している。なぜならば一般道で出せる速度は限られているから。そしてSRというバイクは高速走行に適したバイクではないので、高速道路でもそれほどスピードを出せないと思うから。
では100㏄の差は無意味なのか?
そんなハズはさすがに無く、違いはある。絶対的に違ってくるのが振動の大きさではないだろうか。良い意味では鼓動感が増し味わいが増す。悪い意味では人によってはその大きな振動は不快であろう。
いずれにしても、400も500も良くも悪くもSRであると言える。そして100㏄の差よりもSRであるか否かの方が重要な問題であろう。
あくまでも個人的な見解ではあるが、もしあなたが大型二輪免許を所有しておらず、SR400と500でどちらにしようか悩んでいるならば、私は400をおすすめする。400の新車もしくはなるべくコンディションの良い中古車の方が安全に長く楽しめると思うから。
但し、それでも500が良いと言い切れる人がマニアへの道を進んで行くことは、もちろん応援したい。同じ500仲間として大いに語り合いたいものである。Twitterで待ってます。
さて数字の話はこれくらいにして、次はSRの最大の特徴と魅力のお話しをしたい。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
SRの最大の特徴にして魅力がエンジンをかけるときの「キックスタート」である。
今どきの車はブレーキを踏みながらボタンを押すだけでエンジンがかかる。
今どきのスクーターも似たようなものでキーを回してから、ブレーキをかけならがセルスイッチを押す。
これが普通のバイクになるとギアをニュートラルにしてクラッチを切る動作が入る。そしてすこし古いバイク(キャブ車)になるとこれらに加えて燃料コックを開き、チョークと呼ばれるエンジンをかけやすくする装置のレバーを引く動作が必要。
そしてSR。基本的には他のバイクと一緒であるが、エンジンをかける時に使うボタンもスイッチも無い。その代わりについているのがキックペダル。
このペダルを踏み込んでエンジンをかける。この時に補助的な役割を果たしてくれるのがデコンプ機能。デコンプレバーを握り、目印をあわせてからキックペダルを踏み下ろしてエンジンをかける。
言葉にするとややこしいが、実際にやってみれば至って簡単…
ではない。
簡単ではないが決して無理でもなく、慣れることが出来る。
だが慣れるまではコツが分からないし、寒い季節はなかなかエンジンがかからない。そして毎日バイクに乗っていればよいが、数ヶ月ぶりにエンジンをかけようとすると大変である。
エンジンがかかるまで延々とペダルを踏み続けるのだ。まるで苦行のようなキックスタート。どこが魅力的なのか?
なんといってもその大変なキックスタートを一発で決められたときのカッコよさがいい。そしてたとえ一発でかからなくとも、必死にエンジンをかけ続けてかかった時のうれしさ。
エンジンをかけるだけで喜びのあるバイク。それがSRである。
ご存じの方も多いと思うが、キックスタートはSR以外のバイクにも採用されている。しかし他のバイクはセルスターターとの併用が多い。キックスタートだけなバイクは少ないのだ。
それこそが魅力であると同時に、SRに乗ってみたい人を不安にさせる要素でもあろう。
そうなのだ。バイクで走り始めるまでは自分の都合でどれ程時間を費やしても構わない。しかし一般の公道においてエンストした場合に、すぐにエンジンをかけられない所が最大の難点だと私は考える。
全く自慢にならないが、名古屋の3車線ある国道の真ん中の車線で思いっきりエンストして、後ろのトラックに急ブレーキをかけさせ、あわててバイクを押して車線を横切り路肩を目指した私は、トラックの運ちゃんから「死にてえのかバカヤロウ!!」との怒声を浴びせられたが、全くもってごもっともな言葉だと思った。
そんな体験を話してしまうと尚更キックスタートに不安な印象をお伝えしてしまうが、実はこの問題の発生原因はエンジンの始動方法と全く関係がない。
そう、エンストが問題ならばエンストしなければよいのである。
つまりは私の運転技術が不足していたからこその問題であり、不足していたにも関わらず3車線道路の真ん中を走行していたことにも問題があるだろう。
だからある程度の運転技術がある人ならば何の問題もなくSRを楽しめるはずである。
しかし残念ながら私のように技術が足りないといろいろな失敗談が積み重なってしまうかもしれない。
しかししかし、運転技術もまた向上されていくものでありましょう。向上心のある人もまたSRを楽しめる人だと思う。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
さて最後にとっておきのキックスタートの極意。SRをどう乗るとエンジンがかかりやすくなるかをお伝えして終わりにしよう。
とても簡単にして難しいことだが、『毎日エンジンをかけること』である。これに尽きる。
昨日かかったエンジンが今日かからなくなることはほぼ無いが、3か月前にかかったエンジンが今日かかりが悪いことは当たり前のことなのです。
それではここまでお読み頂きありがとうございました。あなたのSRに対する好奇心を少しでも満たしたり刺激出来たとしたら幸いであります。
次回はSRの苦手な分野であると考えられる高速道路走行について書いてみようかな。
kuruma