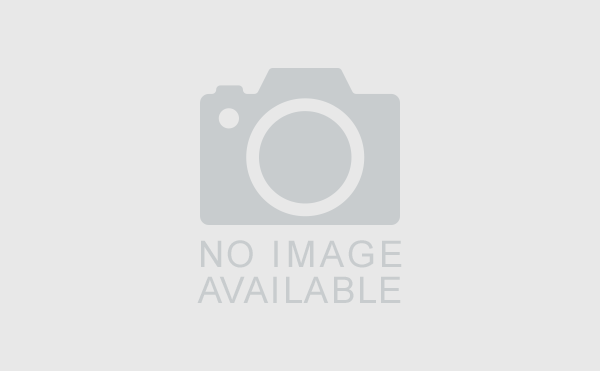梅干し嫌いは克服出来るものなのか?

食わず嫌いという言葉がある。
本来的な意味は食べたことがないにもかかわらず嫌いだと決め込むこと。
そして私は梅干しが苦手だ。食べられないことはないが、食べずにすむなら食べたくない。しかし梅味のポテトチップスや柿の種などのお菓子は好きで、たまに無性に食べたくなる。
この矛盾したような状態を不思議と思わずに暮らしていたがふと、「実は梅干し平気なんじゃないか?」という疑問が湧いた。つまり日々の梅味のお菓子に鍛えられ、梅干しも美味しく感じられるように味覚が変化したのではないかと思ったのだ。
そこで某コンビニの梅干し入りのおにぎりを食べてみることにした。パッケージには『熟成仕立て 紀州南高梅』という梅干し好きにはたまらない、梅干し嫌いにもたまらない文字と、日本人なら見間違えようもない梅干しの画像。
購入時には「これはいけそうだな」と思っていたが、いざ食べる段になると急にソワソワしてしまい、緊張のあまり味がよく分からないまま食べ終わってしまった。
以上のくだりをTwitterでつぶやいてみたところ、心優しい皆さんから温かいイイネと、励ましのお言葉とともに梅干し攻略のヒントも頂いてしまった。
そう私は確かに梅干しが苦手だが、梅が苦手なわけではないかもしれないと勇気づけられたのだ。つまりいわゆる食わず嫌い。梅を食材として考えれば、自分に合った加工・調理方法により梅嫌いが克服できる可能性が見えた気がした。
まったくもってして気のせいかもしれないが、そんな私の自己分析による梅干し嫌い克服のためのレポート。
渾身のゆるゆるな内容ですので、気楽にお読み頂けましたら幸いです。
目次
1、梅干しが苦手な理由
2、どの梅を食べるか
3、克服なるか
あとがき
1、梅干しが苦手な理由
そもそも梅とはなんであろうか?野菜なのか果物なのかも判然としない。
梅干しはご飯のおかずに属するものであるのだから野菜という人もいるであろう。対していやいや梅は樹になるものであるのだからこれすなわち果物であるという人もいるに違いない。
梅が野菜であれ果物であれ珍しい特徴として、基本的に生では食さないことが挙げられる。よく熟したものは生でも食べられるらしいが私は食べたことがない。生の青梅には毒性があるとも聞く。
だからといって、梅を煮たり焼いたりする話もあまり聞かない。つまり多くの日本人にとっては『梅=梅干し』の式が成り立ちやすい。やはり梅といえば梅干しであろう。
そして梅干しは多くの日本人に愛されている。そして私を含めた一部の日本人からは嫌われている。
なぜ嫌われるのだろうか?
一番大きな声として聞こえてきそうな理由は「酸っぱいから」である。しかしこれは私には当て嵌まらない様に感じる。もちろん度を超えて酸っぱいものは勘弁願いたいが、私は酸味が苦手な性質ではない。
では何故か?ここからは一般的な話ではなく個人的な見解である。
ポイントは2つ。味と食感。
まず味について。味の予測が難しいことが嫌である。
梅干しは酸っぱいことが最大の特徴だろうが色々なタイプがあり、酸っぱいのか塩辛いのかはたまた甘いのかどんな味がするのか分からず、味の濃さ薄さの幅も尋常ではない。しかも表面部分の味と噛んだ後の味、さらには種付近の味も違って感じられるものもある。加えてそれを、おにぎりの中に入れてしまったら見た目のヒントすら無くなってしまう。
もうほとんど闇鍋の世界観ではなかろうか?
おそらく好きな方にとっては味の変化も楽しみのうちだと推測するが、ビビりな私にとってはどこまで味が変わるのかを気にしながら食べることはしんどい。
次に食感。こちらも味の部分と似ているが、どのくらい柔らかいのか硬いのか。中身がぐにゅっとなるのかならないのか。繊維を多く感じるタイプか否か。これまた気にするのがしんどいのだ。
いや、気にしなければよいのは解かる。わかるが、気にしないということは私にとって、落とし穴があるけど気にするなと言われているようなものだ。ビクビクが止まらない。
この2つのポイントは、私の梅干しを食べることの経験値不足による部分と、漬け方の差が大きいのであろう。
経験値の不足は言わずもがな。そして漬け方であるが、ややこしい点として梅干しといいつつ干していないものもあるのが素人からするとまた厄介。干す干さないのどちらが良い悪いではなく、どっちのタイプがくるのかで心の準備がまるで違う。
基本的に干してあるものが柔らかく、干さないものがカリカリの食感であろう。この差は大きく、海に行くつもりで出掛けたのに山に到着してしまう位に違いを感じる。
さて、ぐだぐだと苦手な理由を語ってしまったが、そのおかげではっきりとわかってきた。私はとにかく味と食感の不安定感が苦手である。つまりやはり梅自体の味は嫌いではない可能性は残された。
一縷の望みを持って慎重にどんな梅を食べるのが良いか考えてみよう。
2、どの梅を食べるか
梅干しが好きな人であれば、最高級の梅干しが一番美味しいと感じられる確率が高い。私も梅干しを一つ一つ丁寧に個包装したものや、高級そうな桐の箱やいい感じの蓋がついた壺に入っている画像をネットで見ると、それだけで良いものであると信じることが出来る。
しかし美味しいと感じられる自信は無い。しかも当然ながら値段もお高いので却下である。
ここは庶民の味方であるスーパーマーケットにお世話になろう。
自宅から徒歩5分でつく店の漬物売り場へ行くと、折よく梅干しの特設コーナーがあった。梅干しに旬があるのだろうか?
ありがちなプラスチックの透明容器に入った梅干しがズラッと並ぶが、どれもピンとこない。やはり売り場を間違えたようだ。そう、私の本命はお菓子売り場である。梅干しというよりも梅を加工した食品であればこの際何でもかまわないのだから。
過去幾度となく通っている店であり、お菓子売り場であるが、梅のお菓子を探すのは初めてである。果たして見つけることが出来るかと懸念していたが何の苦も無く見つけることが出来た。意外と種類も多く、やはりお菓子売り場でも梅が日本人に愛されていることを感じる。
3種類、選ぶことを先に決めていた。松竹梅理論ではないが、やはり比較対照するには3種類で始めるのが妥当であろう。
Twitterで頂いたアドバイスを思い出しながら、大いに悩み決めた3種類が以下である。
1、やわらかはちみつ梅
2、梅干しシート
3、男梅(ほし梅)

やわらかはちみつ梅は絶対に自分の判断と価値観では選ぶことが出来なかった品である。Twitterでのアドバイスを信じて選んでみた。ここだけの話、ぶっちゃけ一番食べたくないと思える逸品である。梅をはちみつで甘くする発想が、わざわざ辛口で作ったカレーにアンコを入れて甘口にするような違和感を覚えてしまう。
梅干しシートは私の中では大本命。完全に梅を加工して作られているので、例の味と食感の不安定感が皆無であると考えられる。これがダメならもうほとんど望みがないのではないかと思う。
男梅(ほし梅)は売り場の中で一番上級者向きと感じた品。私のような初心者が手を出してよいのか不安であるが、梅干しの良さを鋭い形で凝縮しているであろう所にこだわりを感じた。そして本当に何となくで明確な理由が不明だが、これは食べられるという気がした。気のせいである可能性が果てしなく高いのが不安ではあるが。
さあ、準備はできた。いよいよ実食。
3、克服なるか
まず各個の感想はツイートで報告済みのためそれをそのまま引用させて頂くが、食べる直前の感想としては「買いすぎたな」であった。
勇気を振り絞るというよりは平常心であることを自分に言い聞かせて感情の高ぶりを抑えこみ口に入れる。
【やわらかはちみつ梅】
— クルマ (@aakosodatesedai) March 4, 2021
「はちみつ」の文字から激甘の味付けとベタベタな食感をイメージしたが、嫌な甘みは全く感じず、食感も自然。しっとりしているのにビタビタと汁がしたたることもなく普通の梅干しより食べやすい。書かれていなければ、はちみつを使っていることが分からないかも。種はあった。 pic.twitter.com/aQ2XHwLla0
【梅干しシート】
— クルマ (@aakosodatesedai) March 4, 2021
思ったよりも酸っぱくないので食べやすい。口に入れただけではほとんど酸味を感じず、噛むと酸っぱさがだんだん広がる。梅を食べている感がとても少なく、良い意味で何を食べているのか分からなくなる程。でもちゃんと梅味。主な原材料が梅なことが不思議に感じる。 pic.twitter.com/PPBmvM9JkA
【男梅(ほし梅)】
— クルマ (@aakosodatesedai) March 4, 2021
しょっぱい。そしてカラッカラに乾いた見た目が特徴的。種を抜いてくれてあるので食べやすい。しっかりと中まで乾燥してあるので、硬めの食感ながら均一な噛みごたえで好印象。今回の3種の中では一番梅干しらしさを感じさせる味。 pic.twitter.com/NpG3YSPRGF
さて、まとめとして最初に「で?結果的に美味しかったの?ダメだったの?」の疑問にお答えする。
美味しいと感じられた!
3種3様の味と食感であったが、どの品も美味しいと表現して問題が無い。そして共通点としては、後を引く感じがある。1つだけで食べ終えるのは困難で私もつい2つ目が欲しくなった。
やはり私は梅の味が嫌いではないことがわかり、まさに食わず嫌い。
清水の舞台から飛び降りるくらいの覚悟が必要かと思っていたら、保育園の舞台から降りるくらいの感覚で食べ進めることが出来た。
しかしそれと同時にやはり全ての梅料理を好きになることも難しいと感じる。特に最初にチャレンジした梅のおにぎりは、梅干しとご飯と海苔のハーモニーを楽しむものであろうが初心者には難しすぎる食べ物かと。
私のような梅に苦手意識が高い人は、まず梅自体の味をしっかりと把握が出来る単体での食し方が良いであろう。その際にネックになるのが梅干しの味の濃さ・塩分濃度の高さである。
一般的に梅干しの塩分濃度は20%という数字がベンチマークとなるようで、これを下回ると保存が難しくなる。塩分濃度の目安を少し調べてみたが、みそ汁の塩分濃度が1%位で0.8%が理想らしく、ご飯のおかずは1~1.5%位。この数字と比較するとより顕著に実感するが、やはり梅干しは単体で食すにはしょっぱ過ぎる。
この問題を解決してくれるのが減塩タイプの調理法であり保存料だが、そもそもの保存食品である梅干しに保存料を入れる矛盾と味に影響を及ぼす可能性が難点なのかもしれない。
おそらく一番良いのは、昔ながらの製法で作られた梅干しを塩抜きと呼ばれる技法で塩分を最適な値にコントロールし、最高な塩加減の梅干しを食べる直前に作り出すことと考えられる。
昔の人が「いい塩梅」と表現した様に、塩加減が最適であれば至高な味わいを体験できることだろう。
しかしながら、われわれが日々の忙しい暮らしの中で手軽に食するのには適していない。ではどうすば良いのか?その答えが今回私が食べてみた3品を含む、田舎のスーパーにも並ぶ数々の梅関連食品であろう。
梅干し嫌いを克服するためのルートは色々あると思うが、一番手軽で美味しい道はお菓子売り場にあるというのが私の結論である。梅干し嫌いのかたはぜひ試してみて頂きたい。
そして、未だ本式で本格的な梅干しを食べていないビビりな私のことを、梅干し嫌いを克服したと認定するか、否かはあなたが決めて欲しい。
梅干し嫌いは克服出来るのか?出来たのか?
Twitterで祈りながら審判を待つ。応援してくれたあなたに感謝を捧げながら。
(終)
あとがき
日本の梅干しの消費量は減少傾向にあるようだ。
詳しい数字は分からなかったが『漬物ポータルサイト(全日本漬物協同組合連合会)』の統計・資料欄に経済産業省「工業統計」各県別漬物の出荷金額(年次)の資料があった。少し古いデータであるが、野菜漬物(果実漬物を含む)の出荷金額は平成11年で約5,488億円であったのが平成28年では約3,292億円まで減少している。
おそらく梅干しの出荷も消費量も減っていると思われ、背景には日本人のお米離れや食生活の多様化が考えられる。しかし今回あらためて梅干し嫌いの私が梅の加工食品を味わってみて思うのは、今後も無くなることはないだろうということだ。なぜならば、美味しかったから。食べやすかったから。
梅干し嫌いの私が言うのもだが、伝統的な梅干しは日本の文化であり、後世に残すべきものであろう。それと同時に新たな梅の加工食品もどんどん世に広まればよいと思う。日本以外にも。
食生活の多様化は漬物・梅干しの消費量を減少させたかもしれないが、新たな可能性も広がるかもしれない。インド・イギリスより伝えられしカレーライスに福神漬けやらっきょうを合わせたように。和食が世界に広がったように。
それではここまでお読み頂き、ありがとうございました。最後に梅干しが苦手なウチの末っ子くんのつぶやきを借りて締めくくろう。
カレーはかれえ。梅はうめえ。
kuruma