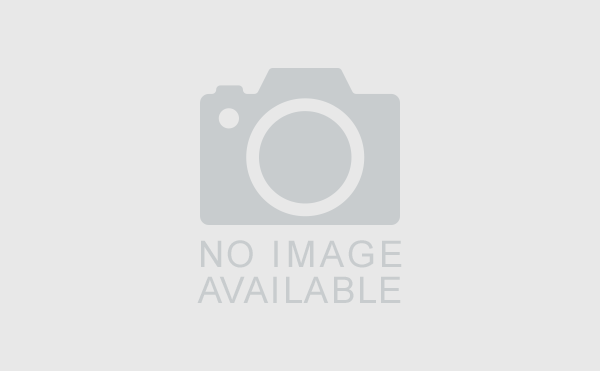娘が吹奏楽部に入ったらフルートを買うことになったよ

今回は吹奏楽未経験の親が、娘のフルートを購入したご報告的なお話しです。ほとんど笑いの要素がないので、あまり面白くない記事かもしれませんが、私達夫婦のように吹奏楽部についての知識がないのに、子供が吹奏楽部に入ることになった人の参考になればいいなと思いながら書いています。
ちなみに私がどのくらい吹奏楽部に対して知識が無いかと言いますと「え?学校に楽器あるんじゃないの?自分で買うの??」というぐらい。
ですから購入前に少しフルートのことを調べたのですが、あまりにも知識が無さ過ぎて何を知っておくべきか見当も付きませんでした。そして結論的には購入したのですが、事前に知っていれば良かった知識を購入後に得ました。
そこで吹奏楽の素人がフルートを購入する際に得た知識を、同じく吹奏楽にご縁のなかったあなたに向けてなるべく分かりやすくお伝えしてみます。
そんな訳で吹奏楽の知識がありませんので、専門的な良し悪しは語れませんが、忖度も無いのでニュートラルな情報をお届けできると思います。フルートについてのみの話となりますが、他の楽器も同じように購入を検討される必要性があるのかもしれませんので、参考になれば。
それでは目次に続きまして本編です。体験談と情報が入り乱れ少しボリュームが多めですが、初めてフルートを購入する前に知っていたら良かったなと思うことを全て詰め込んでみました。
お時間のあるときにゆっくりとお読み下さい。
目次
1、楽器を購入した方が良い理由
2、値段の目安と素材の話
3、メーカーは?(日本に生まれた喜び)
4、お試し(吹き比べ)の重要性
5、新品と中古品について
6、アフターフォローとお手入れ用品
7、まとめ(補足)
1、楽器を購入した方が良い理由
うちの娘は小学校時代は合唱団に入っていましたが、中学校には合唱団がなく吹奏楽部に入部しました。つまりここで初めてフルートに触れることになったので、親子でフルートの知識ゼロでありました。
だから私ども夫婦は学校にフルートがあるのにも関わらす、個人で購入する理由が分からなかったので、率直に顧問の先生に電話をしてお聞きしてみました。
(本来は部活見学の際に顧問の先生とお話しする機会があるようなのですが、コロナ禍の影響で部活見学が中止となってしまいました。)
一番の理由は、学校にあるフルートは古くて状態が良くないから。そして自分に合ったフルートの方が吹きやすくて良いということでした。
な・る・ほ・ど。
そして娘に欲しいかどうか質問してみたところ「そりゃあ欲しいよ」とのご回答。2・3年生の先輩も購入したものを使用しており、指導に来てくれている高校生の先輩も中1の頃に購入したそうです。
そんなわけで入部を決めた頃には思ってもみなかったフルートの購入を検討することとなりました。
なお私の中ではフルートを購入するご家庭というのは、ご両親も音楽をたしなまれており、大きなお家に暮らして白い大きな犬を飼っているようなイメージでしたので、まさか自分がその立場になるとは。。。
2、値段の目安と素材の話
本題です。そう、私にとってもおそらくこの記事を読んで下さっているあなたにとっても、ぶっちゃけ問題点は値段ですよね?
子供の為に楽器を購入するのがイヤな親など極少数。カッコよく買ってあげたいものです。しかし残念ながらお金は湧いてきません。うちは家のローンでヒイヒイです。すみません、話がずれました。
さて恐る恐るネットで検索してみますと、なんとビックリ。セットで1万円台からありました!
なんだ、ビビッて損したな。1万円位からあるならせいぜい10万以内でOKだなと思ったあなたは、私の仲間ですが早合点はお待ち下さい。
さらにビックリしたことに、初心者向けの似たようなセットが50万以上しているものもあるのです。
どうやらフルートの値段の幅はかなり大きいようです。もちろんプロの方が使うものが数百万円しても全く不思議ではないのですが、初心者向けでもこれほど大きな差は驚きでした。
ちなみに顧問の先生に予算の目安をお聞きしてみたのですが、「そこはご家庭のご都合で」という至極ごもっともなお話し。そして同時にぜひ試し吹きをしてみて欲しいとのこと。
そこで楽器屋さんに連絡を取り、実物を見つつ予算を検討することにしました。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
さてここからは楽器屋さんで教えて貰ったことと更にネットで調べたことになりますが、フルートの値段差が大きな一番の理由は素材の違いにありました。
私のような未経験者でもフルートが銀色をしているものだというイメージはありますが、まさに「銀」(元素記号でいうところの「Ag」)そのものが使われていることが多いのです。
そして銀製のフルートと比較して、価格が安いものは「白銅」や「洋銀」が使われており、逆に高いものは「金」や「プラチナ」が使われている。そして実は昔ながらの「木製」のものもあります。
つまりわれわれ吹奏楽の初心者が視野に入れるべき素材は「白銅」「洋銀」「銀」の3種類であり、白銅と洋銀はあまり優位差が語られていないので一緒と考えることにして、あとは「銀」にするかどうかと「銀」がどの位使用されているのかがポイントになります。
銀の使用量が増えると音の響きや深さが増すようですが、当然ながら価格も上がっていきます。金やプラチナ、さらには木製もそれぞれの良さがありそうですが、吹奏楽の初心者の親が気にする必要はないですね。
そしてほとんど銀などの金属素材で出来ているフルートですが、「タンポ」と呼ばれる穴をふさぐ部分の部品などにはちょっと特殊な素材が使われていたりもします。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
それでは次に「銀がどのくらい使用されているのか」について説明するために、秘密の呪文をお伝えします。
トウブカンギンセイ
カンタイギンセイ
ソウギンセイ
これが重要なので繰り返してみましょう。
頭部管銀製
管体銀製
総銀製
ざっくり分かって頂けましたでしょうか?フルートは頭の方(口をつける方)から「頭部管」「胴部管(主管)」「足部管」の3分割されております。
そしてこのうちのどの部分までを銀製とするかで値段が変わってくるのです。
頭部管だけを銀製とするものが「頭部管銀製」であり、「管体銀製」は頭部管にプラスして胴部管と足部管も含めた管の部分が銀製。「総銀製」はさらに管部分のみならず「キイ(指で押さえる部分や動くところ)」も銀製。
またメーカーごとに細かな部分のどこまで銀を使用するかの差もあり、「リッププレート」と呼ばれる吹く時に口を当てる部分だけを銀製にしたものもあります。
(銀製以外の部分には白銅や洋銀が使用されているものが多い。)
もう少し細かなお話しをすると、使用する銀の純度にも差があります。シルバーのアクセサリーがお好きな方はご存じと思いますが銀は金属としては柔らかな素材になりますので、Ag925(スターリングシルバー)のような銀合金の使用が一般的ですが、さらに100%銀に近いものも使用されているモデルもあります。
もちろん総銀製が一番お高くなり、良い品であることは間違いがないのですが、総銀製が一番吹きやすいわけでは無いというのがまた難しいところ。銀の使用量が少ない方が初心者には鳴らしやすいそうなのです。逆に言うと上達してくると総銀製も使いこなせるようになるということでしょう。
つまり「白銅・洋銀」製の良さは値段の安さだけでなく吹きやすさもあり、銀の使用量(どの部分までを銀とするか)も、ただ単にコスト面のことだけを考えている訳ではなく、吹きやすさ・扱いやすさにも関係しているようです。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
さて素材の話をふまえて頂きいよいよ値段の目安の話をしたいのですが、その前にもう一つ。これはフルートや楽器だけに限った話ではありませんが、定価と実売価格は違いますよね?
ですから購入先の値引き次第の部分もあり、素人の調査では限界がありますので、本当にざっくりな目安ととらえて下さい。
★白銅・洋銀製
10万円以下
★頭部管銀製
10万円台~20万円台
★管体銀製
30万円台
★総銀製
40万円台~
もちろん製造メーカーによる価格差や、ネット販売によるお買い得品で価格帯が重なってくることも多々あるかと思いますが、実際に地方都市で物色した体感では、この位でありましたことをご報告させて頂きます。
いかがですか?やはり価格差が大きいですよね?
実は高額なモデルは素材による違いに加えて、もう一つの大きな理由がありました。どうやら基本的にハンドメイド製品。驚いたことに職人さんによる手作りなのです。
しかしながら価格の安いモデルも欲しいですよね。このために白銅・洋銀製の多くは機械での量産品として低価格を実現しています。またモデル・メーカーによっては機械化とハンドメイドの組み合わせにより、コスト低減と高品質のバランスを取っています。
ハンドメイドモデルと量産モデルで価格差があるのは当然のこと。調査を重ねていくうちに高額なモデルの値段の高さにも納得してしまったのでありました。
そして恐ろしいことに、10万円って安いじゃんとか思い始めていたのです。。。
3、メーカーは?(日本に生まれた喜び)
まずメーカーで気にすべき点は、学校で吹奏楽部で指定のメーカーがあるかどうか?かもしれません。
「かもしれません」というのは、娘の通う公立中学校ではそんな心配はなかったのですが、強豪校ですと音質を揃えるためにメーカーの指定があるというネットの書きこみを目にしたからであります。
念のために顧問の先生にも確認しましたが、特に指定はなく本人に合っていることが一番とのこと。しかし逆に言うと本人に合っていないメーカーがあるということでありましょうか?
とにもかくにもネットでメーカーを調べてみますと、聞いたことのない名前が並ぶ中に知っているメーカーがありました!「YAMAHA(ヤマハ)」です。
(全然関係ありませんが私はバイクが好きで、国産ではヤマハが一番好きなメーカーです!)
しかし恥ずかしながら他のメーカーは本当に聞いたことの無いところばかり。そこで娘に学校で使用しているフルートのメーカー名を調べて貰ったところ「Altus(アルタス)」とのことですが、もちろん知りません。
さて、その他の気になったメーカーをざっくり羅列させて頂きます。
「MURAMATSU(村松フルート)」「Pearl(パール)」「SANKYO(サンキョウ)」「MIYAZAWA(ミヤザワフルート)」
いかがですか?名前を耳にしたことがあるメーカーがありますでしょうか?
さあここでクイズです。先の2つのメーカー(YAMAHAとAltus)も含めると6つのメーカーを挙げさせていただきましたが、これらのメーカーに共通することは何でしょうか?
………
……
…
そう、実は全て日本のメーカーなのです!
どうやら日本はフルート大国。戦前から現在まで大きいメーカーから小さなメーカーまで合わせると実に30社以上が存在していたとのこと。
驚きですよね。もちろん海外のメーカーもありますが、嬉しいことに海外のフルート奏者の中にも日本のメーカーを選んでくれる方々がいらっしゃるらしく、メーカーのパンフレットには素敵な皆さんが並んでいました。
残念ながら私はメーカーの違い・特徴を語ることは出来ないのですが、店員さんの話を聞き、メーカーのパンフレットにホームページなどを拝見するとやはり国産メーカーの良さを感じます。
そしてこれは楽器とは何の関係もない話ですが、(作っているものは全然違うのですが)同じ製造業で働いている私としては、日本でのモノ作りが世界に通用していることに喜びを感じました。
娘が吹奏楽部に入りフルートを担当することがなければ知らなかった事実に、ちょっと大げさながら日本に生まれた喜びまで感じてしまいました。
また購入後の感想といたしまして、ネットではなく地元(田舎)のお店で購入する場合は、その店舗での取り扱いメーカーの中から選ぶのが自然であります。ですからいわゆる都会であれば好きなメーカーを選んでからお店を選ぶ、又は多くのメーカーを取り扱っているお店を選ぶことも可能ですね。
それでは下記に6メーカーのホームページのリンク先を張っておきます。全部を見るのは大変なので、まずは気になる3メーカー位を比較してみるといいかもしれません。
★YAMAHA(ヤマハ)
★Altus(アルタス)
★MURAMATSU(村松フルート)
★Pearl(パール楽器製造株式会社)
★SANKYO(三響フルート製作所)
★MIYAZAWA(ミヤザワフルート)
4、お試し(吹き比べ)の重要性
さて購入者本人(我が家の場合は娘)にとっては吹き比べが大切なことは何となく想像出来ると思いますが、我々スポンサー(親)の立場からしても重要なプロセスであります。
何故に親にとっても重要か?
コロナ禍においては学校の部活見学もままならず、我が子がフルートを吹いている姿を見られる絶好のチャンスであり、フルートという得体のしれない高級品に果たしていかほどのお金を投資すべきかの判断を下す絶好の機会だからであります。
加えて購入先のお店を見極める判断材料。
もし仮にネットでの購入を考えているのならば、購入前に貴重な現物を見られるラストチャンスです。
もちろんそれ以上に子供にとっては重大ごと。今後の苦楽を共にする愛器を決めるわけですが、実は喜びばかりではなく緊張と試練の場でもあるのです。
なぜならば吹奏楽をフルートを始めたばかりなのに、いきなり見ず知らずの音楽の専門家と言うべき店員さんの目の前で演奏をするのですから。
この為に入部してすぐの試し吹きはおすすめ出来ません。ある程度の練習期間があった方が良いでしょう。ちなみに私の娘は入部後に1か月以上経ってから行きました。
そしてこれはコロナ禍の今においては特に重要ですが、お店に向かう前に試し吹きが出来るかどうかの確認と予約をしておきましょう。ちなみに私の住んでいる地域にはフルートの在庫がないほど小さなお店しかないので、県内では一番楽器屋さんがあると思われる都市部(高速道路を使って車で1時間くらい)まで足を運びました。
また地方において大きな楽器屋さんですと、吹奏楽部向けにイベントホールなどを貸し切って出張での展示即売会(フェア)のようなものも開催されているようで、当日のみの目玉商品などお得に購入出来るそうです。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
さてさて我が娘の場合で恐縮ですが、試し吹きを2店舗・3メーカー、合計11本のフルートを試させて頂きました。この数字が多いか少ないかは分かりませんが、間違いなく貴重な体験。
1日だけでは決めきれず2日がかりで決めたのですが、これは高額な買い物ゆえに親の気持ちが決まりきらなかった影響が大きく、もう少し事前に価格差の違いを理解していれば、1日で決められていたと思います。
吹き比べてみた娘によれば、やはりそれぞれに差が感じられ、良し悪しは分からずとも「これが吹きやすくてイイかな」という違いは明確な様でした。
また先にフルートの多くはハンドメイド品とのお話しをさせて頂きましたが、このために厳密には同じメーカーの同じモデルでも違いが発生するそうです。ですから試し吹きのメリットはメーカー・モデルの比較もありますが、とにかく自分に合った1本を見つけることが重要なのかもしれません。
購入先のお店については「在庫」を多く持っているお店が理想的であります。これは実際の店員さんから聞いたお話しですが、そのお店では在庫の商品は全て音の鳴り具合などの品質をチェックして良いものだけを置いているそうです。安心ですね。
これは素人考えではありますが、もし仮に試し吹きが出来ない環境であり、ネットで思い切って注文するしかないのであれば、ハンドメイドモデルではなく量産モデルを選んだ方が品質のバラつきが少なく、しかもお買い得なものが購入出来るのかもしれません。
ただやはり大げさに言えば、自分にとっての理想の1本を見つけだそうと思えば、お試し(吹き比べ)は避けては通れぬ道でありましょう。
ちょっとばかり大変な話に聞こえてしまったかもしれませんが、本来的には楽器選びは楽しく嬉しい時間です。親子で楽しく選べたら最高ですね。
5、新品と中古品について
フルートには中古品もあります。新品と中古品のメリットとデメリットは車の新車と中古車で考えれば分かりやすそうです。
新車は高いがしっかりと保証があり、トラブルの心配がほとんどなく、変なクセもついていない。
対して中古車は同じモデルであれば新車よりも安く購入出来るが、メーカー保証は切れていることがほとんどで販売店の保証期間も短め、以前に使用していた人のクセなどが残っている場合がほとんど。トラブルの確率も新品よりは上がってしまいます。
ただし絶番のモデルが欲しい場合は中古でしか入手する方法がないので、これは究極のメリットかもしれません。
つまり我々吹奏楽初心者にとっては、新品の安心感が魅力的に感じられることが自然なことだと思います。
しかしながら限られた予算の中で購入するわけですから、安さもまた魅力的であります。万が一の修理代も視野に入れながらの検討が必要かもしれませんが。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
ちなみに我が家の場合は新品を選択しました。一番の理由はやはり安心感。親にフルートの知識がないために、少しの不調や不具合が許容範囲なのか修理が必要なのか判断が全く出来ないので新品の方が保証を含め安心と考えたからです。
またこれも楽器とは全然関係のない話になりますが、うちの娘は第2子であり長男のお下がりで済ませてきたものが多々あります。そして私の仕事の都合で収入がガクンと減った時期に小学校の入学を向かえており、勉強机や椅子を祖父のお古や中古で用意したりもしてきました。
ですから新品のフルートを緊張しつつ恥ずかしがりながらも、一生懸命に試している娘に最高級品は買ってあげられなくとも新品にはしてあげたいなと思ったのです。
つまり車で例えてみますと、高級車を中古で購入するのではなく、軽自動車を新車で購入するイメージですね。
あまり参考にならないお話しをしてしまいましたが、お金に余裕があれば新品に越したことはなく、予算を抑えたいないならば中古品も大きなメリットがあると感じました。
6、アフターフォローとお手入れ用品
フルートの購入が決まれば親の役割はほとんど終わったようなものですが、子供とフルートの関係はようやくスタート地点に立ったばかり。ここからが本番とも言えます。
そんな中で気になるのがアフターフォロー。購入後にトラブルが発生してしまった場合の対処法ですよね。
ネットで購入するにしてもお店で購入するにしても、考えておきたい部分です。もちろん購入とメンテナンスを割り切って考えるのも一つの作戦だと思いますが、実際の店舗で購入するならばやはり手厚いフォローを期待したいものです。
つまりはフルート選びの最終段階として、購入店の決定も重要な要素であり、もしかしたらお近くに店舗が一つしかなく選択の余地がないかもしれませんが、修理対応をどのようにして貰えるのかは確認しておきましょう。
ちなみに私どもが選んだお店は家からそこそこ遠いのですが、娘が通う中学校はもちろん地元の高校の吹奏楽部とつながりがあるそうで、修理依頼は学校を通して行えるとのことで心強く感じました。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
そしてフルートに限った話ではありませんが楽器には日々のお手入れが必要不可欠。
お店によるとは思いますが、サービスでお手入れ用品を付けてくれるところがありますので、値段交渉の際はしっかりと確認しておきましょう。
お手入れ方法はおそらくすでに子供たちは部活の中で教わっていると思いますが、不安な点があればお店の方に聞いておきたいですね。
アフターフォローとお手入れ用品まで視野に入れて頂ければ、購入の判断材料としては一通りだと思われます。後は総合的に判断して頂ければと思いますが、「値引き」について少しだけお話しを。
今回2つのお店で最終的な金額を出して貰いましたが、どちらも定価ではなく値引きがありました。しかしながら一方のお店はアフターフォローに力を入れているからこれ以上の値引きは無理といった感じ。もう一方は交渉次第ではさらに値引いてくれそうな気配がありましたが、先のお店と比較しておどろく様な値引きはありませんでした。(それぞれの取り扱いメーカーは異なります)
ですから単純に値段だけを比較すれば、ネットで最安値を探した方が安いであろう金額でありましたことをご報告させて頂きますが、これは予想通りなお話しですね。
7、まとめ(補足)
かなりボリュームのある内容となってしまいましたが、いかがだったでしょうか?以上が購入前に知っておけば良かったなと思う事柄であります。
どうしても昨今のコロナ禍においては、じっくりとお店に通う・複数のお店を見て回ることが難しい情況ですから、ある程度の予備知識があると楽器選びがスムーズに行えると思います。
またこれは繰り返しとなってしまいますが、お店に行くときは必ず事前に電話などで予約することを強くおすすめさせて頂きます。お店の規模にもよりますが、試し吹きが出来る部屋やスペースには限りがあり、おそらく対応出来る店員さんの数にも限りがあります。
そもそもお店の規模が小さいとフルートの在庫が無く、試し吹きが出来ない可能性もありますね。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
それでは最後に補足の知識として、おそらく調べていくと気になること3選をお伝えします。
(1)カバードキィとリングキィ
多くの初心者向けのモデルはカバードキィと呼ばれキィになっていますが、リングキィと呼ばれるキィもあります。これは指で押さえるキィ部分に穴があいているかどうかで、カバードは開いていないので初心者でも扱いやすく、リングは穴が開いているので正確に穴を指で押さえてあげる必要があります。
リングキィには諸々のメリットがあるようですが、吹奏楽部でフルートを初めて触る初心者にはカバードキィが良さそうですね。
(2)Eメカ
Eメカとは「Eメカニズム」の略称で、「E」というのは「ミ」の音のこと。どうやらフルートは3オクターブ目のミの音を出すのが非常に難しいらしく、これを何とかしてくれるのがEメカ。
こちらは日本のメーカーも海外のメーカーも導入しており、主流となっている技術らしいのですが、普通のドレミも分からない私にはどの位の恩恵があるのか見当もつきません。しかし初心者にとってはあればうれしい機能でしょう。
(3)インラインとオフセット
左手で扱うキイの並び方が直線的なのがインライン。左手の薬指で押さえるキイを少しずらして配置し、扱いやすくしているのがオフセット。
見た目で選べばキイが真っすぐ綺麗に並んでいるインラインですが、初心者にとっては演奏のしやすさ・キイの抑えやすさが何よりなのでオフセットされている方が良いと思います。音の差もあるようなのですが(インラインの方が良さそう)、娘の試した11本のフルートの違いがよく分からない私には、聞き分けは難しいこと間違いありません。
以上、おそらく調べていくと気になること3選、いかがだったでしょうか?
吹奏楽素人の私からみますと、単純に初心者向けは「カバードキィ」「Eメカ有」「オフセット」で問題ないと思われました。
しかしながら各メーカーで細かな技術の差やこれ以外の共通の機能もあるようですので、信用出来るお店と店員さんへの出会いが何より重要かもしれませんね。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
今回はあえて我が家で購入したメーカー・モデルはおろか、比較したメーカーも記載を避けさせて頂きました。
これは素人である私の思い込みでミスリードしたくなかったからですが、そうは言っても参考にお知りになりたい方もいらっしゃるかもしれません。もしお知りになりたい場合はTwitterにてお問い合わせいただけましたら、こっそりとお伝えしますね。
日本のメーカーだけを記載させて頂いたのは、フルートについて何も知らなかった私が、日本で多くフルートが作られていることに感銘を受け、ぜひ日本製を購入したいと思い調査が偏った結果であります。
最後の注意点といたしまして、私と同じく日本製を手に入れたいかたは、メーカーによっては海外工場によるコスト低減モデルがあることをお伝えしておきます。逆に予算を抑えて購入したい人はかなり狙い目のモデルかもしれませんね。
(下記はパールの台湾工場にて作られているモデルだそうです。)
それではここまでお読み頂きありがとうございました。あなたのフルート選びの参考にほんの少しでもなりましたら幸いです。ぜひ満足のいく納得の愛器を手に入れて下さい。
kuruma