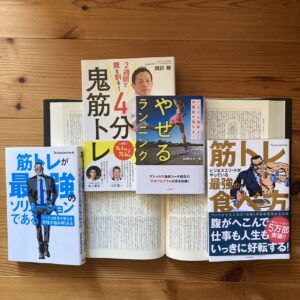狂言クラブ
あなたは人前で話しをすることが得意でしょうか?とっさに言葉が出てこなくて困った経験はありませんか?
今回は私の人生の中で一番アドリブで乗り切るべきだったのに出来なかった日の話を、記憶が曖昧過ぎて断言出来ないことが多すぎた為に、少し創作を加えた私小説として書きました。
以前にツイートした『郷土歴史研究クラブ』(こちらを序章として記載)の続編でもあります。
気分転換にお読み頂けますと幸いです。
それでは目次・序章に続きまして『狂言クラブ』のはじまりはじまり。
目次
1、序章
(郷土歴史研究クラブ)
2、狂言クラブとは
3、棒に縛られる
4、アドリブ
5、あとがき
1、序章
(郷土歴史研究クラブ)
大昔(平成元年頃)の話であるが私の中学生時代に、部活とは別にクラブ活動というものがあった。クラブの内容は将棋や手芸など様々あり、定員も決められていた。自分が何を希望したか忘れてしまったが、希望したクラブに入れず、どこでもいいと言った結果『郷土歴史研究クラブ』に所属することになった。このクラブはとても不人気で私を含め3人しか居なかった。
研究のテーマは地元の古墳について。古墳と言えば『前方後円墳』が有名だが、もちろんそんないい代物は無かった。それでも実際に見に行くことになり、郷土にも歴史にも興味は薄かったが、それなりに期待しつつ出掛けた。
古墳は思っていたより山の方にあり、まずは自転車で移動。途中からはアスファルトで舗装された道がなくなり、自転車で進むのは厳しくなったため、木の間を枯れ葉に足を取られながら、本当に道が正しいのか不安に駆られながら徒歩で進む。すると不意に木々が少ない窪地が現れ、唐突に小さな看板が有った。
どうやらここが目的地。よくよく見れば窪地の真ん中あたりがこんもりしており、コレが古墳かな?と思えないことも無い。同行者は「すげぇ!古墳だ!」と喜んで写真も撮っていたが、私は無感動。口には出さなかったが「ショボ」と思っていた。
そして実はもう1つ古墳がありそちらにも行く予定であったが、想定していたよりも時間がかかったので、一旦帰宅してから再集合することになった。
帰宅した私は足が疲れ果てておりお腹も空いていた。そして何より古墳がつまらなかった。ようやく気付いたが私はこのクラブに向いていない。
集合時間を過ぎたころ玄関のチャイムが鳴った。無視した。意外とあっさり聞こえなくなったチャイムに安堵しつつそのまま寝てしまった。
翌日、昨日はどうしたのかと聞かれたが適当な言い訳を答えつつ、逆にもう一つの古墳の話を聞くべきかと思ったが全く古墳に興味が無くなった私は何も聞けなかった。
郷土歴史研究クラブで学んだことは世の中には凄い古墳とショボい古墳があり、クラブは自分でしっかりと選ぶべきで、私のとった行動は一般的に『居留守』と言われる名称だったこと。
後日談だがクラブの存続には最低3名が必要であり、翌年から郷土歴史研究クラブはその歴史に幕を降ろした。さもありなん。
2、狂言クラブとは
あれから1年。またクラブを選ぶ時期がやってきた。クラブ活動は部活動と違い1年単位で所属するクラブを選択する。もちろん同じクラブを選ぶことも可能。ちなみに私は水泳部である。
郷土歴史研究クラブで、クラブ選びの重要性を学んだ私が選んだのは将棋クラブ。
元来インドア派の私にピッタリであり、特に好きと言うわけではないが駒の動きくらいは知っており、将棋さえやっていればいいので簡単である。昨年の疲れを癒やすのにはうってつけと考えた。
しかし実は将棋クラブは大人気で、某クラブとは違い競争率が高く定員をはるかに超える申し込みがあった。私の運が悪かったのか、よこしまな考えが将棋の神様の怒りに触れたのかあえなく落選。
そんな私に声をかけてきたのが、狂言クラブの顧問だった。
狂言クラブの『狂言』とは、いわゆる『能』と並び称される日本の伝統芸能のアレである。野村 萬斎(のむら まんさい)さんや、和泉 元彌(いずみ もとや)さんが狂言師としては有名だと思うが、チョコプラの「そろり そろり」の方が有名かもしれないのは、蛇足。
さて、狂言クラブは郷土歴史研究クラブに勝るとも劣らぬ不人気クラブ。例のクラブ存続3名以上ルールに引っ掛かり存続の危機。私に声がかかった時点で2名しか応募がなかったそうだ。しかしながら歴史だけはやたら長く、顧問としては自分の代で廃止は絶対に避けたいところ。しかもこの顧問が私の所属する水泳部の顧問でもあった。
顧問は必死だったような気がする。その熱意に負けたような、ジュースをおごって貰えるというような噂に釣られたような、あやふやな動機で私は狂言クラブに所属することとなった。
同学年の生徒3名と顧問でのクラブ活動が始まるが、なぜかこの4人はみんな水泳部。
そしてもしかしたらここが一番の悲劇なのかもしれないが…全員が男である。
3、棒縛り
狂言クラブの活動は狂言をすることであり、研究をするわけではない。秋に行われる文化祭での舞台に立たなければならないのだ。全く興味が無いのに所属してしまった私としては当然のごとく裏方を希望。
そして希望は半分だけ叶えられた。
つまり舞台に立ちつつ裏方もやるのが当たり前なのであった。演目は2つ。私が担当するのは『棒縛り』というお話し。
棒縛りはかなり有名で楽しいお話しなのだが、当時の私は知る由もなくセリフの多さと古く独特な言い回しで書かれた台本にうんざりしつつ、まず取り組んだのは舞台で使う棒の作成。念願の裏方の仕事からであった。
ここで棒縛りの内容をざっと説明するが、ネタバレ全開であるのはご容赦頂きたい。
登場人物は3名。あるお屋敷の立派なご主人と、その使用人でお酒が大好きな二人、太郎と次郎。この使用人コンビがメインのお話しだが、一番の主人公は棒術(長い棒を使った武術)が得意な次郎であると思われる。
ちなみに配役はご主人役を顧問がつとめ、太郎役が私、次郎役が同級生である。
ではあらすじ…ある日、主人は出かける用事があった。しかし、日頃からお酒をこっそりと盗みのみをしてしまう太郎と次郎をそのままにして出掛けるわけにもいかず、作戦を立てた。
主人は太郎を呼び出し、次郎をこらしめるからと協力要請。太郎了解し、次郎の得意な棒術をやらせておだて、その隙に主人と二人がかりで次郎の両手を案山子(かかし)のように棒術の棒に縛り上げた。
次に主人は太郎の不意をつき、両手を後ろ手に縛り上げることに成功。二人を縛り上げた主人は安心して出かける。
残された二人は仲良く反省…する訳もなく、口喧嘩してからなんとか酒を飲もうと行動開始。酒樽にたどり着くが、それぞれ縛られているので自分の口には杯が届かない。そこで次郎が太郎へ、太郎が次郎へと縛られた手で何とか杯を口へと運び、代わる代わる酒を飲むことに成功。
次第に酔いがまわり調子に乗って、飲めや歌えや踊れやのどんちゃん騒ぎ。
そこへ主人が帰ってきてこっぴどく叱られ、逃げ惑う…というお話しである。
棒縛りと言うだけのことはあり、棒に縛られながらも何とかして酒を飲むという行動と、その動きのコミカルさが最大の見せ場である。はずなのだが、なにせ素人の私にはセリフが難しく頭になかなか入らない。
例えば冒頭は主人の独り言(太郎次郎への愚痴)からはじまり、太郎を呼び出すのだが、
主人:「まず太郎冠者を呼び出そう。やいやい太郎冠者、居るか」
太郎:「はあー!」
主人:「いたか」
太郎:「お前に居りまする」
主人:「思いの外早かった。お前を呼び出したのはほかでもない。」
こんな具合の言葉を使う。
さらに分からないのが動きに対して擬音のようなセリフがあるが、これいらんだろうと思えるものだ。例えば太郎と次郎が縛られた後で、座る・立つシーンのセリフが「えいえい、やっとな」。まあ、「よっこいしょ」みたいなものかもしれないが、二人同時に言うのでなおさら不要な気がした。他にも私のセリフではないが、次郎が戸を開けるシーンでは「ぐぁら、ぐぁら、ぐぁら、開いたわ、開いたわ」と、自分で「ぐぁら」言うのが変である。
そしてセリフを覚えるだけで大変なのにさらに困るのは、発音が分からないことだ。日常生活の中で口にしたことのない言葉だらけで、意味さえ分からないものもある。
これが普通の部活、例えば演劇部であれば、当然美人の優しい先輩がいて、我々新入部員を手取り足取り優しく指導してくれるであろうが、なにせ一年間限定の不人気クラブには先輩もおらず、狂言はもちろん演劇すら未経験な水泳部員が3人だけ。頼りにすべきはずの顧問も素人であった。
さてこんなとき、あなたならどうするであろうか?
今の私なら、まずググる。そしてYouTubeでも見ながら進めるだろう。しかし当時はスマホどころかインターネットも普及していない。
では、どうしたか?
何も調べなかった。つまり中学生男子が「多分、こんな感じだろう」と想像だけで練習を進めていく。今にして思えば無謀である。日本の伝統芸能を舐めていると言われても否定できない。しかし誰も止めてくれなかった。
勝手な妄想ではあるが、もし女子が1人でもいてくれたならば多少はブレーキが利き、もう少しまともな方向へと進んだことであろう。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
セリフもようやく覚えてきたところで舞台稽古。実際の体育館ステージを使用して練習する日がやってきた。ここでさらに困ったことが起きる。歌と踊りが分からない。
そう、このお話しには太郎と次郎が酔っ払ってどんちゃん騒ぎをするシーンがあり、盛り上がってきたところで謡を歌い、舞を舞うと台本にちゃんと書いてある。しかし私たちは聞いたことも見たこともない。
そこで協議を重ねた結果、「謡は無理だから無しで良いのではないか?」「舞はなんとなく動けば良いのではないか?」という結論に至った。
常識で考えればこれはもちろんダメである。もう一度言おう。ダメである。もはや無謀を通り越して狂言への冒涜ですらある。しかし、残念ながらだれも止めない。無知とは悲しいものである。
一般的に狂言は喜劇であり、見る人は気軽に楽しめば良いと言われているが、鑑賞のポイントとして『謡・舞・語り』の3点が挙げられる。狂言を習うときは歌や舞の稽古から始めるとも聞く。しかしど田舎の水泳部、男子中学生3人組はそんなこと知らない。
そして顧問は自分のことで頭が一杯だったのか、やはり何も知らなかったのか、自分が歌う踊るシーンがないのをよいことに一切口を挟まなかった。只々、ひたすらに台本を読んでいた姿に頼りなさが一段と増しただけであった。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
美人の優しい先輩もいない、頼りがいのある素敵な顧問もいない、そんなわれらが狂言クラブの誰も知らない長い歴史を感じさせる品が衣装であろうか。段ボール箱に詰められたそれを開封して衣装合わせを行った。
衣装は3点セット。着物に袴をはき、肩衣(かたぎぬ)と呼ばれる袖の無い上着のようなものを羽織る。肩衣は肩を張らせたようなデザインであり、これと袴でようやく狂言らしくなってきた。
そしてもう一つ狂言クラブの持ち物として存在しており、唯一の舞台のセットでもあるのが『松』。
日本人であれば誰しも一度はなんとなく目にしたことがあるであろう、舞台の上になぜかさらに屋根付きの舞台があり、その正面には大きく描かれた松。
そんな舞台で演じられる演目を『松羽目物(まつばめもの)』と言われるらしいが、そんなことは露知らず。段ボールと画用紙が主材料と思われる松を確認しつつ、出番の前日に体育館ステージにどう貼り付けるのかを打ち合わせして準備を終えた。
4、アドリブ
いよいよ迎えた文化祭。われらが狂言クラブの舞台は2日目、演劇部の前に発表するプログラムである。そうだった。我々素人集団とは違い、演劇をガチで行っている集団がいたのである。演目は『夕鶴』定番でありながら感動すること間違いないお話し。
別に争っている訳ではないので同じ舞台に立つもの同士で仲良くしても良さそうなものだが、なにせ活動の熱量が違い過ぎてしまい交流は一切なかった。
そして文化祭のパンフレットには「狂言がございますから祖父母のかたも是非ご観覧ください」的なことが記載されていた。敬老の日と同じ月だったせいもあるかもしれないが、われわれにそんな期待を懸けて良いものだろうか。そんな期待があるなら、クラブの人員を増やすべきであろう。
全校生徒に加えて保護者、さらにはじいちゃんばあちゃんを迎え入れた体育館で幕が上がる。
文化祭2日目、最初に行われたのが『棒縛り』であった。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
自分でも意外なほどに緊張はしていなかった。良くも悪くも練習はしてきたし、自分のセリフだけはとにかくしっかりと覚えた。相方の次郎役の同級生は私と違い勉強も良く出来るタイプで成績優秀。記憶力もよく心配がない優等生だ。
心配なのは主人役の顧問であったが冒頭一人で舞台に立ちセリフを喋り始めると、朗々と響く声でなかなかのものである。見直した。
すぐに主人に呼ばれ、私・太郎も舞台に立つ。
主人:「まず太郎冠者を呼び出そう。やいやい太郎冠者、居るか」
太郎:「はあー!」
主人:「いたか」
太郎:「お前に居りまする」
主人:「思いの外早かった。お前を呼び出したのは~」
順調な滑り出しである。そして主役の優等生・次郎を呼び出して棒縛りの名前通りに棒に縛りつけるが、ここまで観客は無言で無音だが面白いシーンもないので無理もない。
優等生・次郎を縛り上げて調子に乗っていた私・太郎の背後に、主人役の顧問が回り込み私の手を縛る。そして優等生と私に留守番を申し付け、顧問は舞台を後にした。ここから二人の見せ場である。
まずは例の「えいえい、やっとな」で腰を下ろし、ひとしきり口喧嘩。和解して二人で酒を飲むべく行動開始だが、なにせ本当に縛られているので立つのも一苦労。この辺で笑いがおきるとやっている方は嬉しいが、自分が観ていたら今の観客同様にクスリともしないであろう。
優等生・次郎が「ぐぁら、ぐぁら、ぐぁら」とありもしない戸を開けて、酒盛りが始まる。このお話しの設定で私が一番秀逸だと思うのが、棒で案山子(かかし)のごとく縛られた次郎と棒ではなく後ろ手に縛られた太郎という、縛り方に差をつけたところだ。これにより互いの不自由さが若干違うので出来ることが違う。
つまりおそらく、この互い違いの状態でいかにおもしろく酒をこぼすか飲むか、飲ませるか飲ませて貰うのかが、狂言師の腕の見せ所であろう。絶対に自分ひとりでは飲むことが出来ない太郎と次郎の、やり取りとその困難に打ち勝ったあとの悪乗りが魅力。
だが見せる腕のない私達にとってはセリフを言いつつ、とにかく何とかお酒を飲んでいるかの様に動くだけで精一杯であり、相変わらず客席は咳ばらいをするのもはばかられるような静かさを保っている。
そして唐突にその時が訪れた。
私・太郎のセリフに対して、優等生・次郎が答えない。どうやらセリフを忘れてしまったようだ。3秒、5秒、10秒。今まで十分に静かだった客席がさらに呼吸を止めてしまったかのように息を飲んでそのまま。
これは無理だと思った私・太郎は、アドリブで進めようとしてセリフを考えた。
本来私が次に言うべきセリフは「何と、このような躰(てい)で舞が舞われるものか」であるが、太郎からの要請がないのに言ったら変である。
そこで「じゃあ俺が舞でも舞ってみるから見ててよ」と伝えたいが、それを狂言の言葉でどう言えば良いのかが分からない。声が出ない。
そこからさらに30秒は優に超えた時、優等生・太郎がついに「ま、まてくれい」。ようやくそれっぽいセリフが出てきたが、その時私は「じゃあ俺が~」を翻訳することで頭が一杯になっており、本来のセリフを忘れてしまっていた。
舞台で見つめ合う優等生・太郎と私・次郎。太郎の目は助けを求めるがごとく心なしか潤み、顔は上気している。私はその想いを受け入れきれずに目をそらす。が、それではまずいと思い直し、太郎に対して「本来のセリフをもう一度考えて言って、時間を稼いでね。」との願いを込めて、視線を合わせた。
すると間髪入れずに「舞ってくれい!」。優等生・太郎の大音声が静まり返っていた体育館に響き渡る。
もう言葉は不要である。私のみならず、今まで会場で狂言ってなんだろうと思っていた人までもが、このあと私・太郎が何か舞うんだねと認識出来たことであろう。
私・太郎は無言で動き始めた。
前へ1歩。右へ3歩。左へ3歩。後へ1歩。
例の「舞はなんとなく動けば良いのではないか?」作戦を決行したのであるが、狂言の鑑賞ポイントである『謡・舞・語り』の謡を排除して、語りも飛んでしまった上に、舞が舞いに見えないのだから、三回目であるが言おう。ダメである。
そしてこの意味不明な舞と呼べる訳がない動きの後から私の記憶は、ものすごくあやふやなものになる。
そのあやふやな記憶によると、その後は謡も舞も出てこないせいか無難に進み、最後のシーンで主人役・顧問のムダに朗々と響く声に叱られながら、優等生・次郎と共に私・太郎は舞台を後にした。
舞台を降りる時に大きな拍手が聞こえた気もするが、気のせいである可能性が高い。
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇
こうして私にとって生涯で唯一の狂言の舞台に幕が下りた。
その後に行われたもう一つの狂言の演目は、名前もストーリーもきれいさっぱり忘れてしまったが、こちらにも顧問がチョイ役で登場し、もう一人の水泳部員がほぼ一人芝居の様なことを行い、それはそれは堂々としたものであった。実は彼、生徒会長に立候補して惜しくも落選してしまったが立派に生徒会の議長を務めあげた大男。今回のお話しではあまり出番がなかったが、ナイスガイとは彼のことである。
さらにその後に行われた演劇部による『夕鶴』は、見る人の心に訴えてくるものがあり、流石はと思える感動の舞台であった。舞台に立つ人のみならず照明や音響の担当も素晴らしい出来栄え。特に『おつう』役の演劇部部長の演技には目を見張るものがあり、才能と練習の成果であろう。
それらに比べてしまうと自分の担当した棒縛りは何とも締まらないものであり、いたたまれない気持ちになったが、どうにもしようのないことであった。
後日談を少し話すと、あの時3名ルールで存続の危機であった狂言クラブの翌年の運命は全く知らないが、あの日が最終公演でなかったことを願うばかりである。そして優等生・次郎は私とは別の高校へと進み、相変わらず優等生であると伝え聞いた。
さらに月日は大きく流れて25年後。縁があり訪れた母校では、郷土歴史研究クラブはもちろん狂言クラブもあの超人気クラブであった将棋クラブさえも何の痕跡も残さずに消えていた。
そして演劇部と水泳部は存続しており、むべなるかなと。
【完】
5、あとがき
まずはここまでお読み頂けましたこと、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
今回のお話しは約30年も前の私が中学時代の出来事を元に一部、脚色を付けて私小説の様なものとして書きました。
冒頭で少し(Twitterでも少し)触れましたが、昔の記憶すぎて思い出せないことが多すぎた理由の一つが、意味不明な舞と呼べない謎の動きのダメージかもしれません。
記憶は美化されると申しますが、美化されてなお恥ずかしい限りな私のクラブ活動に、なんらかの意味があるとは思えませんでしたが、こうしてひとつの文章に書き上げることが出来たことは感慨深いものがございます。
読んで下さいましたあなたに何か伝わるものが御座いましたら幸いであります。
もしご感想などお寄せ頂けますと泣いて喜びますので、Twitterか問い合わせフォームよりよろしくお願い致します。
それでは今一度、感謝を込めて。ありがとうございました。
kurma